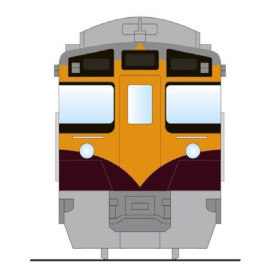京浜急行電鉄は4月15日、新たに導入するロングシート・クロスシートの転換が可能な車両、新1000形20次車(1890番台)1891編成を、報道陣に公開しました。

この車両は、形式こそ新1000形のグループですが、座席のほか、車体形状や接客設備など、多くの面で従来車両の違いがあります。大きく変化した車内や、京急初採用となった「sustina」など、従来車とは別形式と言えそうな新1000形20次車。車内を中心にご紹介します。
ロングシートとクロスシートに転換可能な座席を装備
まずは、20次車一番の特徴である、車内から見ていきましょう。


京急では現在、全ての座席がロングシートの車両(1500形、新1000形の一部)、車端部のみクロスシートの車両(600形、新1000形の一部)、全ての座席がクロスシートの車両(2100形)の、大きく3つの座席配列があります。
この20次車では、座席指定列車や貸切イベント列車に対応するため、ロングシートとクロスシートの転換が可能な「L/C座席」を、京急では初採用。京王5000系や東武70090型のように、ライナー列車での快適性と、一般列車でのスペース確保を両立した車両となりました。



座席は、2列+2列の回転式シートを、扉間に3列配置。座席裏にはドリンクホルダーを設けているほか、座席基部には電源コンセントを設置しています。


また、乗務員室の直後には、前方を向いた展望席が設置されました。京急によると、設置理由は「特に要望があったわけではないが、お客様に楽しんでいただくため」とのこと。600形や2100形には設置されていたこの座席ですが、2002年デビューの新1000形1次車以降は通常のロングシートとなり、2007年以降の新1000形ステンレス車では、座席そのものが廃止されていました。

なお、600形や2100形では展望席横の窓は戸袋窓となっていましたが、この20次車では幅約10センチの細いものに。「明るさのために窓を設置したかったが、機器スペースの問題から、このような形状となった」ということです。

20次車では、トイレも設置されました。こちらも京急では初採用の装備です。2号車にはバリアフリー対応トイレ、3号車には男性用トイレを設置しており、長時間の利用者や貸切列車運転時に配慮しています。



「sustina」を京急初採用
車内が大きく変化した、新1000形20次車。車両外観もこれまでの車両とは異なっています。
これまでの新1000形は、多くが向かって前面左側に非常口を設置したデザインでしたが、20次車では、前面中央部に貫通扉を設置し、連結時に他編成と行き来できる車両となりました。2016年に登場した新1000形1800番台同様、地下鉄乗り入れに対応した装備で、地下鉄区間で求められる編成間の通行を可能としています。


また20次車では、京急では始めて、総合車両製作所の「sustina」を採用した車両となりました。これまでの車両と異なり、車体側面に目立つ継ぎ目は無いほか、側面上部の雨どいは車体と一体化しています。
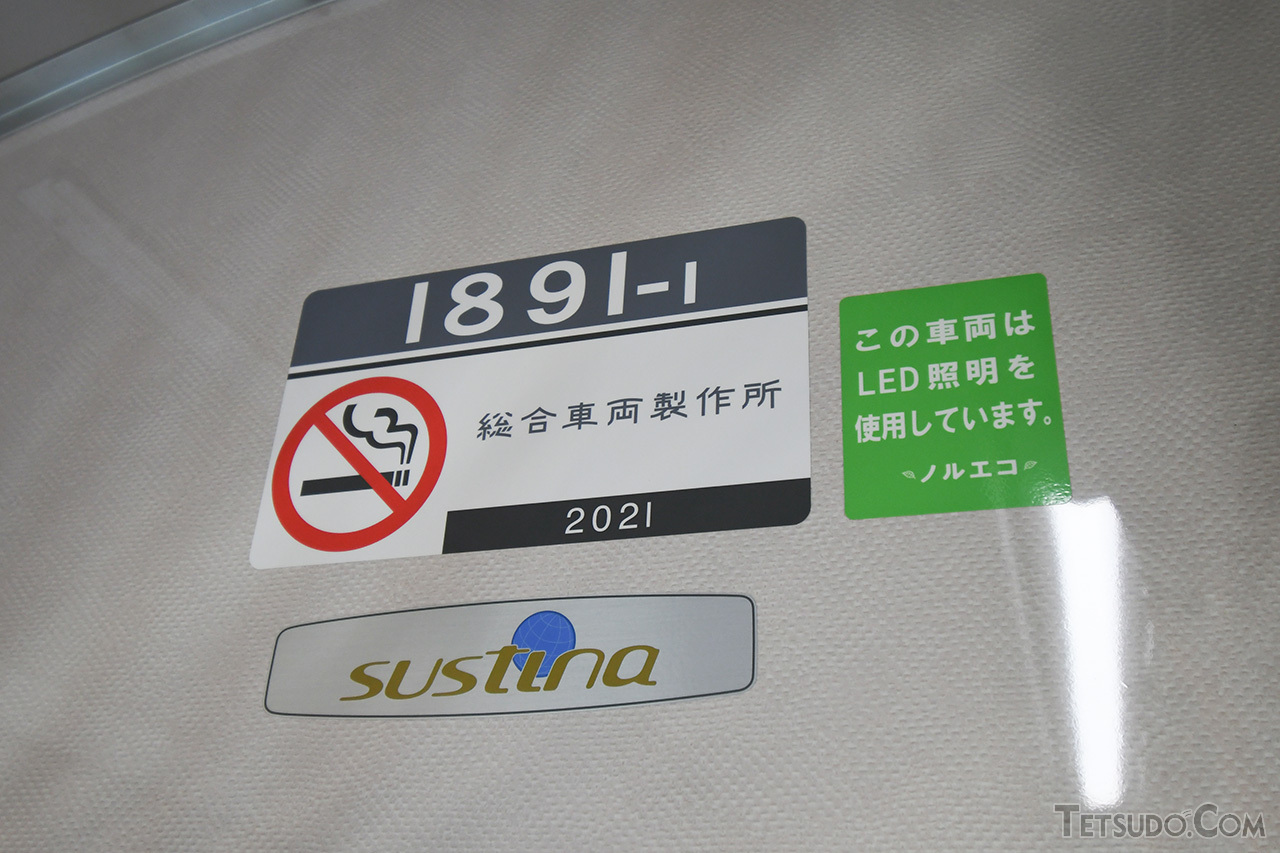

現地にいた総合車両製作所の担当者に質問してみると、「sustina」とは、総合車両製作所のプラットフォームを活用して製造した鉄道車両に冠するブランド、だということです。今回の20次車では、設計こそ川崎重工業と共同開発だったそうですが、車体設計は総合車両製作所が主体となり、同社の18メートル級車両用プラットフォームに基づいて設計したため、sustinaブランドに含まれる車両になったということです。
余談ですが、sustinaブランドの車両によく見られる特徴として、車体側面に溶接の継ぎ目が無い、あるいは雨どいが車体側面上部と一体化している、といったことが挙げられます。しかしながら、sustinaとは上記の通り、同社のプラットフォームを活用した車両のブランドです。そのため、JR東日本のE129系や、しなの鉄道のSR1系のように、雨どいが一体化していない車両であっても、sustinaブランドに含まれるのだそうです。
今回はホーム上からの見学だったため、足回りを見ることはできませんでしたが、20次車では床下機器類にも大きな変更が加えられています。
新1000形のステンレス車では、全車両にモーターを搭載した組成が基本でしたが、20次車では両先頭車にのみモーターを搭載した、2M2Tの組成に。制御装置にはハイブリッドSiC適用VVVFインバータ制御を採用し、SIVは待機2重系となりました。
車両の機器配置としては、モーター搭載車には制御装置も搭載することが一般的ですが、この20次車では、制御装置は付随車となる中間車に設置しています。これは、地下鉄に直通するための基準に定められている、35トン以内という重量制限をクリアするためのものとのこと。20次車では、L/C座席を設置したことで重量が増え、両先頭車は34.5トンとギリギリの数値となっています。そこで、付随車となる中間車に重い制御装置を設置することで、制限をクリアしています。


この新1000形20次車は、5月6日に営業運転を開始する予定。朝時間帯の座席指定列車「モーニング・ウィング」3号に投入され、三浦海岸~金沢文庫間は4両編成、金沢文庫~品川間は2100形と連結した12両編成での運転となります。
なお、20次車は地下鉄への直通に対応した設計ではありますが、京急によると、現在のところ直通運転に使用する予定はないということです。
【4月15日追記:一部表記を訂正いたしました】
有料会員に登録すると、新1000形20次車(1890番台)1891編成のL/C座席の転換シーンや運転台の様子などが、動画でご覧になれます。
スペシャル動画(2分5秒)